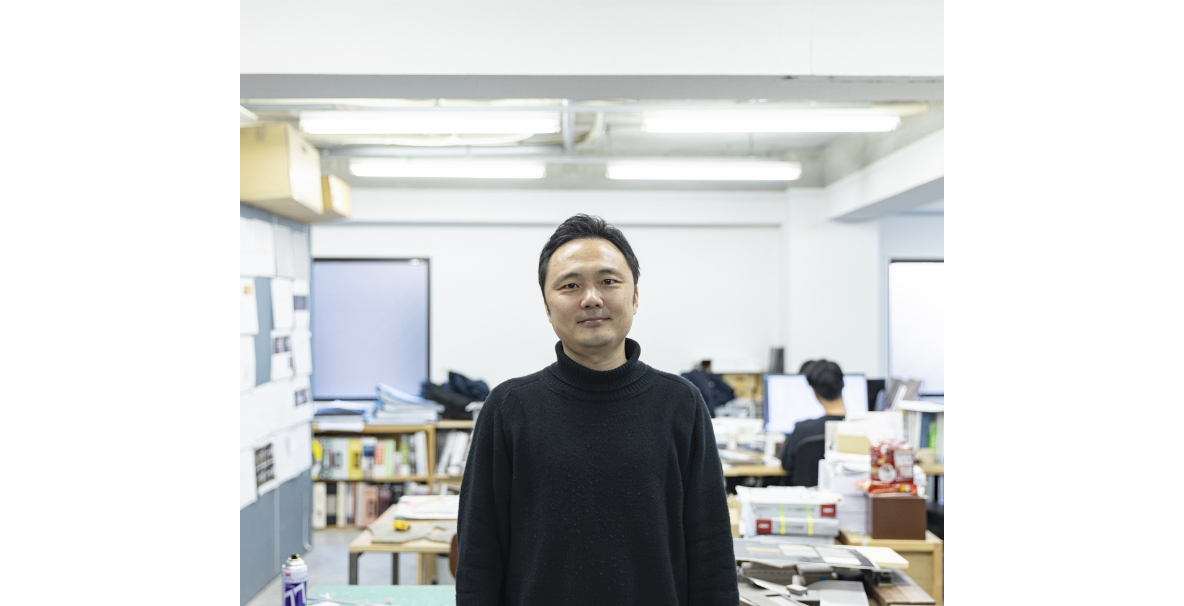VOICE FROM vol.5
―山雄和真 建築家のまなざし、
またの名は「文化的感受性」―
共同創業者/パートナー、東京事務所代表
山雄和真

ウェルネストホームが目指す、未来の子どもたちに向けた持続可能な暮らしとまちづくり。そこで私たちと理念を同じくし、丁寧な時間と暮らしを育むヒト・モノ・コトから、最良の未来へとつなげるための共通項を見つけていきます。
今回のゲストである山雄和真さんは、東京とドバイに拠点を構えるwaiwai合同会社の共同創業者です。北海道ニセコ町のまちづくり「ニセコミライ」では高性能賃貸住宅を設計し、東京花小金井モデルハウスではグッドデザイン賞2023を受賞するなど、ウェルネストホームにとっては欠かせないパートナー。その哲学について問いかけると、「文化的感受性」という建築家のまなざしが見えてきました。
建築の世界に駆り立てた空間の力
「高校生のとき、伊勢神宮の航空写真を見たんです。20年に一度、社殿などを新しく造り替える『式年遷宮』はご存知ですか? 広大な森のなかで、現在の社殿と次の社殿のための敷地だけがぽっかりと空いている写真。その風景がすごく衝撃的で……人間の欲望のようなものがはっきりと見て取れたんです。人の手が介在することによって立ち現れる空間があること。その空間をつくる建築という行為があること。これは一生をかけるに値するんじゃないかと……建築について無知ながら、その深さのようなものを、10代なりに感じ取っていたように思います」山雄和真さんは、建築の原体験を穏やかな口調で振り返ります。東京とドバイに拠点をもち、アジアから世界を見つめるwaiwai合同会社の共同創業者。現在の活躍のきっかけになったのは、たった一枚の風景写真だったのです。

山雄さんは京都に生まれ、高校ではキャプテンを務めたほどのサッカー青年でした。進学校に在籍し、同級生は医者や弁護士を目指すのが当たり前という環境。そこで天邪鬼の気質を発揮してか、まったく想像できない分野であった建築に興味をもち、京都大学の建築学科に進むことになったといいます。
「建築の勉強を深める前、今度は写真でなく直に近代建築の力を体験したことも大きかったでしょうね。一回生の終わりの春休みにフランスを旅しました。目当てはル・コルビュジエの建築作品。代表作のサヴォア邸は予備知識がありすぎて、大きな感動はなかったのですが……ラ・ロッシュ=ジャンヌレ邸に衝撃を受けたんです。様式美から脱却した、空間としての建築物の力、建築家のヴィジョンのようなものを身体的に受け取ったような気がします」

近代建築の巨匠による洗礼を受けた山雄さんは、後に竹山 聖教授の研究室に進みます。数多くの建築家を輩出してきた、通称「京大竹山研」。なにをするにも空間が必要なのだから、すべての学問が建築と無関係ではあるまい。そんな考え方に基づくゼミは、建築の話をいっさいせずに哲学や物理学の読書会を開催するなど、山雄さんの好奇心を大いに刺激しました。
「そういう環境に身を置いていたから、普通の会社勤めができない人間になり、建築家になると腹をくくらざるをえませんでした(笑)。竹山先生は、建築という概念を心から愛していた方です。建築しか自分にはないというほどのお人柄。好きなことを追求する背中を見て、口に出しては言われませんでしたが、学生ながらメッセージを感じ取っていたように思います。『建築が好きなのか? それなら建築家になればいいじゃないか』って」
その場所にない建築の文化や観念
建築家になるまでの半生を山雄さんが語ったのは、waiwaiの東京事務所でした。蔵前に位置し、両国国技館が近いことから、元横綱である稀勢の里の湯呑みを愛用。約10名のスタッフが働く事務所は若手中心かつ多国籍な顔ぶれで、建築設計事務所特有の張り詰めた緊張感とはまた異なる雰囲気です。京都大学を卒業後、東京大学大学院を修了した山雄さんはシーラカンスアンドアソシエイツトウキョウ(CAt)に入社します。日本きっての建築設計事務所に在籍したことが、waiwaiの設立にも結びつきました。
「CAtで最初に携わったのが中央アジア大学のプロジェクトでした。キルギス、カザフスタン、タジキスタンの3ヶ国をまたぎ、キャンパスを同時建設するというもの。3、4年がかりの仕事をいっしょに担当していたのが、waiwaiの共同創業者であるワイル・アル・アワーと寺本健一です。気心の知れた仲間たちと、海外の人も交えてフラットな関係を築きながら、ワイワイやりたい。そんな思いから2018年にwaiwaiを設立しました」

最初は個人事務所として独立したものの、手詰まり感があったと山雄さんは言葉を続けます。しかし、先に独立していたワイルさんが構え、寺本さんが合流していた事務所があるのはドバイ。東京とドバイという8,000kmもの隔たりをまたぐ建築設計事務所は、類を見ない試みといえるでしょう。
「そうですかね……僕らからすると、けっこう自然な話だったんですけど。いままでにない建築をつくるにはどうすればいいのか。東と西の両端から、アジアをサンドイッチすれば、アジアでたくさん仕事ができるんじゃないかって(笑)。CAtを共同主宰していた小嶋一浩さんは、『量が質をつくる』という考え方でした。僕ら3人とも小嶋さんのもとで実務経験を積んでいましたから、実作をつくることができる環境を重視したんです」
そうした姿勢を示すものとして、山雄さんは最近、「建築を広げる」という言い方をしているそうです。「その時点で建築の文化がないような場所。仕事の取り組み方から考えなければいけないような土地。僕らが建築を届けていきたいのはそういう世界ですし、そのほうが可能性もあると思うんです。ヨーロッパとか、アメリカとか、すでに建築の文化が確立されたところに建築家が入っていったって、世界は変わりません。ある種のコミュニティのなかで建築をつづけたって、世界における建築のポーションは増えません。建築を広げるように仕事をしていくことで、僕らにしかできない空間がつくれるような気がしています」

建築を軸に置くことで、世界のいろいろな場所を見たい、知りたいという欲望もあることを、山雄さんは笑って付け足しました。ウェルネストホームとの出会いもまた、大好きな土地という北海道のニセコ通いがきっかけです。
「ニセコの知人から創業者の早田宏徳さんを紹介され、いっしょに食事をしたのが最初でしたが、僕は衝撃を受けました。住宅をつくることに、これだけ情熱を燃やす人がいるなんて知りませんでしたから。高気密や高断熱にこだわり、適した建材が日本になければわざわざドイツからだって輸入してしまうほど。ただでさえ堅いイメージのある住宅業界に、ベンチャーのように新規参入して、本気で奮闘しています。いまでもすごく興味がありますし、好きなんですよね。ウェルネストホームという会社や、早田さんという人間そのものが」

山雄さんがウェルネストホームと出会い、早田と意気投合したのは、ニセコミライのマスタープランが設計された後だったといいます。ゼロベースから取り組むような普段のプロジェクトとは異なる関わり方ながら、ニセコミライ第一弾のモクレニセコA棟にひと工夫を施しました。
「生活のささやかな気配を誘起するように、『雁木』をランダムにまとわせました。建物のひさしを長く張り出す雁木造りは新潟など雪国でおなじみの伝統的な技法ですが、北海道は町の歴史が浅いため、あまり見られません。冬が厳しい北海道の建築は、どうしても閉鎖的というか防御的になってしまいがち。でも、夏ってめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。冬と夏に両方対応できるような空間が北海道にこそ必要だとずっと考えていました。すでにマスタープランがあるなかで、そこになかった観念のようなものを持ち込めたという点で、これもまた『建築を広げる』ことだったと思います」

山雄さんと出会わなければ、ウェルネストホームからは生まれなかっただろう空間。グッドデザイン賞を受賞した、東京の「EGAKU IE 東京花小金井モデルハウス」にも通底します。早田さんと惹かれ合うからこそ、その住宅に新たな軸を持ち込みたかったと語りました。
「花小金井では、住宅を『ひらく』ことをコンセプトに、生活の振る舞いに応じた窓周りのバリエーションを設計しました。ここまでの窓際を徹底的に気持ちのいい空間にしようっていうのは、それまでのウェルネストホームではおそらくなかった観念。高気密・高断熱の住宅がいくら正解だとしても、人間の身体って快適さだけを必要とするわけではない気がしませんか? 風の出入り、雨の匂い、ちょっとした暑さや寒さ。そうした反応を身体の根本的な快楽と捉え、快適さとは別軸で住宅に取り入れようと考えました」

携えるのは「文化的感受性」
「ただ、いずれも僕らの作品だと言いたいわけではありません。建築家ではなくプロジェクトの作品をつくるという意識をwaiwaiでは大切にしています」
雁木にしても、窓周りのバリエーションにしてもそう。waiwaiにしかつくれない空間といっても、シグネチャーになるような建築ということではなく、プロジェクトごとにコンセプトも建築も変わっていくという考え方。追求すべきは、プロジェクトがほしがっている建築はなにかということなのです。
「僕らは『文化的感受性(cultural sensitivity)』と定義しています。先入観をもたずフラットにその土地を観察して、物事の背景のようなものを感じ取る姿勢。難しいことですが、これがおもしろいから、建築をやっているという言い方さえできます」 建築を広げていかなければいけない世界に、「文化的感受性」を携えていくこと。アジアをサンドイッチするwaiwaiの仕事は、そうした哲学に基づいて生まれているのでした。
建築を広げていかなければいけない世界に、「文化的感受性」を携えていくこと。アジアをサンドイッチするwaiwaiの仕事は、そうした哲学に基づいて生まれているのでした。
「中東の建築はどうしても、海外から著名な建築家なりデザイナーなりをオイルマネーで連れてきて、ゴージャスな空間をつくるというのが主流です。中東生まれのアラブ人による建築設計事務所も最近は少しずつ生まれていますが、現状はやはり健全といえないでしょう。ヨーロッパやアメリカは、建築の概念が生まれた土地ですが、近年は空間そのものよりもプロジェクトのストーリーが重視されるようになっています。環境問題や社会問題への姿勢が評価の対象として最優先される状況。その点、日本の建築というのはすごく豊かな文化だと僕は思います。建築の快楽に素直というか、エクストリームに振り切っているというか。世界のどこにもない空間って、日本人によって考えられたものがけっこうあるんですよ。あとはその使い方というか、社会にどう還元していくかが問題。普遍的な価値をもった空間をちゃんと増やしていくこと、諸問題に向き合いつつ空間に建築の快楽を織り込むこと。日本の建築の未来には、建築家のこうした姿勢が求められていると思います」 豊かな建築の文化は、なにも建築家だけによって築かれるものではありません。文化の一員として私たちにどんなことができるか、最後に山雄さんがヒントを挙げてくれました。
豊かな建築の文化は、なにも建築家だけによって築かれるものではありません。文化の一員として私たちにどんなことができるか、最後に山雄さんがヒントを挙げてくれました。
「好きな建物をひとつでも見つけてみてください。小難しく評論する必要なんてないんですよ。おいしい食べ物、楽しい音楽、おもしろい映画。そういうカルチャーと同じ感覚で建築を捉えてくれる人が増えれば、建築の文化がもっと豊かになっていくはずです。竹山研の教えに戻るわけではありませんが、建築とは空間を扱う仕事。地球という空間にいるのなら、要はすべてが建築。建築とは世界を理解するためのメガネのようなものであり、それを手に入れられたのは本当に幸せなことだと僕は思っています」